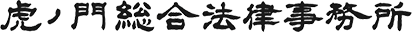パブリシティ事件参考論文と判例
| 判例の種目ないし論文 | 出典 |
|---|---|
| マーク・レスター事件 東京地裁昭和51.6.29判決 |
最新著作権関連判例集 |
| スティーブ・マックィーン事件 東京地裁昭和55.11.10判決 |
最新著作権関連判例集III |
| おニャン子クラブ事件 東京地裁昭和61.10.6決定 |
最新著作権関連判例集V |
| 中森明菜事件 東京地裁昭和61.10.9決定 |
最新著作権関連判例集V |
| 藤岡弘事件 富山地裁昭和61.10.31判決 |
最新著作権関連判例集V |
| 「BOOWY」「光GENJI」事件 東京地裁昭和63.10.13決定 |
最新著作権関連判例集VII |
| おニャン子クラブ事件(2) 東京地裁平成2.12.21判決 |
最新著作権関係判例集IX |
| おニャン子クラブ事件(3) 東京高裁平成3.9.26判決 |
最新著作権関係判例集X |
| 肖像権について 大家重夫/編著 |
最新肖像権関係判例集 P.919以下 |
| パブリシティの権利とその展開 阿部浩二 |
打田先生古希記念 現代社会と民事法 |
| 肖像写真の利用 研究会代表 秋吉稔弘 |
著作権関係事件の研究 P.367以下 |
| パブリシティーの権利と「有名人」概念 三浦正広 |
青山社会科学紀要 22-1 P.1~20 |
| パブリシティーの権利(二) 豊田彰 |
政経研究30巻4号 P.39~57 |
| パブリシティの権利と不当利得 | 注釈民法(18) P.554~ |
| パブリシティの概念と法的性格 播磨良承 |
判例時報1050号 P.15~ |
| マルチメディア・デジタル化時代の 肖像権の形成とその対応大家重夫 |
マルチメディア&グローバル 戦略特別セミナー |
| プレスの自由とパブリシティの権利 豊田彰 |
政経研究36巻1号 |
| 商品化権とパブリシティの権利 加藤恒久 |
特許管理26巻4号P.343 |
映画の著作物に関する著作権法の規定のまとめ北村行夫
- 著作権法は、第10条において、著作物をいくつかの観点から分類して例示している。
その一つである「映画の著作物」は、その意義、権利者、権利内容等について、他の多くの著作物と異なっており、しかもそれらの規定は、同法の中に散在している。よって、一まとめにして概観しておくことは、実際上の便宜に叶う。 - 特別な内容を有する規定とは、(1)映画の著作物概念(著作権法第2条 条3項)、(2)映画の著作者(第16条)、映画製作者(第2条1項10号)、と著作権の法定譲渡(第29条)、(3)頒布権(第26条)、(4)映画の著作物の保護期間(第54条)である。この他に、これまでは上映権を挙げていたが、平成11年の改正により同権利は映画特有の権利ではなくなった(第22条の2)。
- 映画の著作物概念(著作権法第2条3項)に関する判例
(1)映画の著作物について言及しているのは、著作権法第2条3項である。
が、これについて、述べる前に見落してはならないことは、当該映画が著作物といえるためには、まずもって、同第2条1項1号の著作物の要件を充していなければならない、という点である。したがって、単に、街頭にビデオカメラを捉え付けてランダムに移りゆく風景を録画したからといって、それが常に映画の著作物となるわけではない。
(2)したがって、第2条3項は、この事を踏まえたうえで、著作物の中における映画の著作物概念ないし要件を「明らかに」したものである。
が、そこでは、立法時に存在した劇場用映画を基準とした「映画の著作物」が何であるかについて、直接には定義していない。同項は、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ物に固定されている著作物を含むものとする。」と定め、立法後生ずるであろう「映画的」表現形態に対応すべく、劇場用以外の映画概念の外延を画するという規定の仕方を採った。
そのため、従来の劇場用映画は、当然法的に映画著作物であるが、それと視聴覚的効果の類似するビデオ(録画・再生の技術手段の差異はあるが)についても、映画概念に含むこととなる。もっとも、これについてもこれを異とする判例がある。
(3)問題は、更にその後に生じたビデオゲームないしコンピューターゲームである。
(イ)これについて、リーディングケースとなった判例がある。東京地裁昭和59年9月28日のいわゆるパックマン事件判決である。そこには、詳細な判断が展開されている。
(ロ)ところが、これを覆す判決が出された。東京地裁平成11年5月27日のいわゆる「中古ゲームソフト」頒布権侵害事件の判決である。
そこでは、パックマン事件と全く異なるアプローチにより、ゲームソフトが、映画の著作物ではないとされ、よって頒布権侵害は成立しない、とされた。
しかし、同判決の採用した映画著作物概念は、東京高裁の平成13年3月27日の判決によって退けられた(但し、同高裁判決は、パックマン事件と同じくゲームソフトが映画の著作物とは認めたものの、別の理屈を採ったため、結論は変えていない。)。パックマン判決の概念を踏襲した判決は、東京高裁のみではない。
同事件に類似する大阪の中古ゲームソフトの事件では、大阪地裁がパックマン事件判決を踏襲して、今回の東京地裁と異なる判決を出し、大阪高裁もパックマン事件判決の構成を踏襲したが、結論的には頒布権侵害にならない、として大阪地裁判決を覆した。
(4)こうして眺めてみると、パックマン判決における映画の著作物概念は維持されることで、ほぼ固まったと評価してよい。 - 映画の著作者、映画製作者と映画著作権の法定譲渡
(1)著作権法が100年余り前に登場した時、著作物は個人によって創作されるものであり、またそれら著作物のジャンルは著作物ごとに別種のものと想定されていた。しかし、その後、集団による創作や、異なる種類の統合した著作物を意識せざるを得なくなった。そのような著作物の典型が映画の著作物である。
(2)映画の場合、脚本や美術あるいは音楽、カメラワーク等によって統合的、集団的に創作されるのが通常である。
そこで、このようにして成立する映画を、そうした複数の著作物と複数の著作権の集合として見ることも不可能ではなかったが、著作権法は、実態に即して端的に一個の著作物と認めることとし、したがって、それらを一個の統一体とした者を、すなわち「全体的形成に創作的に寄与した者」を著作者とする、ということにした(第16条)。
監督と呼ばれる者がそれに当たるのが通常であるが、これに限られるわけではない。
(3)しかし、映画製作の実態は、多額な資金や高度な分業、それを統合する能力などを前提としており、創作能力のみでは映画著作物が現出しない。そこで、映画の制作に「発意と責任を有する者」を「映画製作者」と名付け、映画著作物の制作プロセスに法的に位置付けを与えることとなった。
その位置付け方は、国によって異なる。トルコのように映画製作者が著作者である立法や、イギリスのように映画製作者が本来的に著作権を有するという立法や、フランスのように反対条項のない限り、著作者から映画製作者へ著作権が譲渡されたと推定することとした立法もある。
日本は、「法定譲渡」という規定をしている(第29条)。すなわち、映画の著作者が、映画製作者との間で「参加契約」を結んでいるときは、映画の著作権は、映画の著作物がその完成の瞬間に、何らの意思表示なしに映画製作者に譲渡されるとしているのである。
(4)映画の著作者は、したがって、著作者ではあるが、著作権者とはならない(論理的には、一瞬の間だけ著作権者だった、というべきであるが、現実論としては、その権利行使の機会を得ない)。したがって、著作者が行使しうるのは、著作者の権利から著作権を除いた権利、すなわち著作者人格権(著作権法第18~20条)のみである。
もとより、監督の団体からは、このような日本の法制へ強い批判がある。が、ここでは立ち入らない。
(5)ところで、映画が完成した場合に、第29条の法定譲渡がされるとしても、完成しなかった場合はどうなるのか。
また、完成しても、「未使用フィルム」について、誰が権利を有するのか。
更に、このような点が問題となるなら、そもそも「完成」とはどういう状態を指すのか。
これらを巡って裁判となった事例がある。東京高等裁判所平成5年9月9日のいわゆる三沢市勢映画製作事件がそれである。
判決は、完成によって法定譲渡が生ずるとし、ここにいう完成とは当初予定されていた映画としての完成までも意味するものではなく、撮影済みのフィルムが、編集されるなどによって映画としての創作性を生じて完成に至るとした。
そして映画として未完成の場合のフィルムを「映像著作物」とし、映画の著作物したではないから著作者に帰属したままであるとした。同判決は、最高裁において肯定された(最二小、平成8年10月14日判決)。 - 映画の頒布権
(1)映画の著作物に与えられる特殊な権利としては、頒布権と上映権があった。しかし、上映権は、平成11年の改正により、映画以外にも及ぶこととなったので、頒布権のみが映画の著作権の特殊な内容ということになる。
(2)また、他の著作物にも与えられている貸与権(第26条の3)は、映画の場合には、同条によって与えられるのではなく、頒布権の中に含まれるとされている(第2条1項19号、第26条の3カッコ書き)ので、このような規定の仕方という点においても特異となっている(なお、念のために付言しておくと、書籍・雑誌の貸与権については、著作権法の附則第4条の2で当分の間は、貸与権が及ばないことになっている。)
しかし、映画の著作物の全ての貸与権が、頒布権の中に含まれない、という何とも奇妙な解釈も傍論的にではあるが中古ゲームソフト判決によって示されている。(4)を参照されたい。
(3)更にいえば、映画以外の著作物については、平成11年の改正により譲渡権が認められるとともに、適法な第一譲渡により、譲渡権が消滅するとの規定が設けられたので、消滅の有無の点を除いては、映画の著作物と他の著作物との間には立法条の差異が減った。
(4)ところが、かかる整理は、中古ゲームソフトに関する東京高裁、大阪高裁の判決によって混沌たる状況になっている。
(イ)中古ゲームソフトに関する大阪高裁判決は、頒布権も又、譲渡権同様に消滅するものである、とした。
(ロ)また、類似事案に対する東京高裁判決は、頒布権が生じる映画の著作物の複製物とそうでない映画の著作物の複製物という区分けを行い、大量複製されない映画著作物にのみ頒布権が生ずるので、ゲームソフトは、そもそも頒布権が生じないとした。
N.Y州の制定法に示されたパブリシティ権
51条 差止・損害賠償訴訟
本州において、前条に定める書面による同意を得ないで、自己の氏名、肖像画、肖像写真ないし声を、広告の目的または商業の目的で使用された個人は、本州の上級裁判所において、自己の氏名、肖像画、肖像写真ないし声を使用している個人、会社または企業に対して、当該使用を差止めるために、衡平法上の訴訟を提起することができる。また、当該使用によって被った損害の賠償を請求し、回復を求めることができる。さらに被告が、本章の第50条において禁止されているかまたは不法であると規定されている方法によって、故意に使用した場合には、陪審はその裁量によって、懲罰的損害賠償を課することができる。しかし、本条は、個人、会社ないし企業が、本条が適法であるとする方法で使用するために、かかる氏名、肖像画、肖像写真および声を含む素材を、氏名、肖像画、肖像写真および声の使用者に対して、いかなる媒体においても販売その他の譲渡をすることや、これらの使用者に直接または間接に販売または譲渡する目的で第三者に対して販売その他の譲渡をすることを、妨げるものではない。本条は職業として写真撮影を行っている個人、会社または企業が、制作した作品の見本を展示することを妨げるものではない。ただし、かかる個人、会社または企業が、対象となっている個人から異議を申立てる通知書を受領した後も同様の行為を継続する場合は、この限りではない。本条は、個人、会社および企業が、製造業者または取引業者の氏名、肖像画、肖像写真および声を、当該製造業者または取引業者が製造し、制作し、または取り扱った製品および商品であって、かかる氏名、肖像画、肖像写真および声を使用して販売また取引されたものに関連して使用すること、あるいは、著作者、作曲家または芸術家の氏名、肖像画、肖像写真および声を、かかる氏名、肖像画、肖像写真および声を使用して販売または取引された文学作品、音楽または芸術作品に関連して使用することを妨げるものではない。本条は、録音物を処分、取引、ライセンスまたは販売する権利が、契約書またはその他の書面により、生存している個人またはかかる権利の保有者から授与されている場合に、録音物の著作権者が、かかる録音物を第三者に対して、処分、取引、ライセンスまたは販売することを禁止するものではない。前記の記述は、連邦法または州法により授与されているその他の権利または救済を廃止または制限するものではない。
(内藤篤ほか一名 著『パブリシティ権概説』木鐸社巻末資料より。なお、本資料の転載許諾は、内藤篤先生のご好意による。ここに記して感謝の意を表明する。)
カリフォルニア州の制定法に示されたパブリシティ権
3344条 広告または勧誘における
(a)他人の氏名、声、署名、写真または肖像を製品もしくは商品上において、または製品、商品またはサービスの広告、販売または購入勧誘の目的で、当該人(当該人が未成年者の場合にはその親もしくは後見人)の事前の同意を得ないで、いかなる方法においてであれ故意に使用した者は、その使用を理由として当該人が被った損害を賠償する責任を負うものとする。さらに本条に基づいて提起された訴訟においては、本条に違反した当事者は侵害を受けた当事者に対して、(1)750ドルないし、(2)無権限の使用の結果として侵害を受けた当事者が被った損害額のより大きい方の金額、ならびに無権限使用を理由としてその使用から得られた利益額で損害額算定の際に要素として参入されなかった金額につき、賠償責任を負うものとする。その利益額の証明においては、侵害を受けた当事者は、無権限使用から得られた総収入額を証明することのみを要求され、本条に違反した当事者はその総収入額から控除されるべき費用を証明することが要求される。侵害を受けた当事者のために懲罰的損害賠償を認めることもできる。本条に基づく訴訟において勝訴当事者は、弁護士費用および報酬を求めることもできるものとする。
(中略)
(d)本条の目的において、ニュース、公共的な事項、スポーツの放送もしくは記事、または政治的なキャンペーンに関する氏名、声、署名、写真または肖像の使用は、(a)項に基づいて同意が要求される使用には該当しないものとする。
(e)商業媒体における氏名、声、署名、写真または肖像の使用は、単に、その使用を含む素材にコマーシャル目的のスポンサーが付いているか、または有料の広告を含んでいることのみを理由として、(a)項に基づいて同意が要求される使用には該当しないものとする。むしろこれは、氏名、声、署名、写真または肖像の使用がコマーシャル目的のスポンサーシップまたは有料の広告と直接的に関連つけられることによって、(a)項に基づいて同意が要求される使用に該当することになるか否かの事実認定の問題とする。
(以下略)
990条 広告または勧誘における物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像
(a)物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像を製品もしくは商品上において、または製品、商品またはサービスの広告、販売または購入勧誘の目的で、(c)項に定める人物の事前の同意を得ないで、いかなる方法においてであれ使用した者は、その使用を理由として当該人物が被った損害を賠償する責任を負うものとする。さらに本条に基づいて提起された訴訟においては、本条に違反した当事者は侵害を受けた当事者に対して、(1)750ドルないし、(2)無権限の使用の結果として侵害を受けた当事者が被った損害額のより大きい方の金額、ならびに無権限使用を理由としてその使用から得られた利益額で損害額算定の際に要素として参入されなかった金額につき、賠償責任を負うものとする。その利益額の証明においては、侵害を受けた当事者は、無権限使用から得られた総収入額を証明することのみを要求され、本条に違反した当事者はその総収入額から控除されるべき費用を証明することが要求される。侵害を受けた当事者のために懲罰的損害賠償を認めることもできる。本条に基づく訴訟において勝訴当事者は、弁護士費用および報酬を求めることもできるものとする。
(中略)
(k)商業媒体における氏名、声、署名、写真または肖像の使用は、単に、その使用を含む素材にコマーシャル目的のスポンサーが付いているか、または有料の広告を含んでいることのみを理由として、(a)項に基づいて同意が要求される使用には該当しないものとする。むしろこれは、物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像の使用がコマーシャル目的のスポンサーシップまたは有料の広告と直接的に関連付けられることによって、(a)項に基づいて同意が要求される使用に該当することになるか否かの事実認定の問題とする。
(以下略)
(内藤篤ほか一名 著『パブリシティ権概説』木鐸社巻末資料より。なお、本資料の転載許諾は、内藤篤先生のご好意による。ここに記して感謝の意を表明する。)
マークレスター事件判決抜粋(東京地裁 S51.6.29判決 S46(ワ)9609号事件)
(一) 氏名及び肖像に関する利益の法的保護
通常人の感受性を基準として考えるかぎり、人が濫りにその氏名を第三者に使用されたり、又はその肖像を他人の眼にさらされることは、その人に嫌悪、羞恥、不快等の精神的苦痛を与えるものということができる。したがって、人がかかる精神的苦痛を受けることなく生きることは、当然に保護を受けるべき生活上の利益であるといわなければならない。
(中略)
社会構造が複雑化、高度化し、マスコミニュケーション技術が異常な発達を遂げた現代社会は、常に個人の氏名や肖像が多様な形式で他人に利用され、公表される危険性をはらんでいるが、かかる危険が高まるに従って、逆に各人の、その氏名や肖像を他人にさらさずに生きたいという願望が強くなるというのが、現代人に共通の意識と考えられるのみならず、我国の法制がよって立つ個人尊重の理念は、かかる利益に対する不当な侵害を許容しない趣旨をも含むと解されるからである。かような人格的利益の法的保護として、具体的には違法な侵害行為の差止めや違法な侵害に因る精神的苦痛に対する損害賠償が認められるべきであって、民法709条にかかる違法な侵害を不法行為と評価することを拒むものと解すべき根拠は存しない。
(二) 俳優等の氏名、肖像に関する利益
人が自己の氏名や肖像の公開を望まないという感情を尊重し、保護することを主旨とするものであるが、俳優等の職業を選択した者は、もともと自己の氏名や肖像が大衆の前に公開されることを包括的に許諾したものであって、右のような人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある。
(中略)
俳優等が自己の氏名や肖像の権限なき使用により精神的苦痛を被ったことを理由として損害賠償を求め得るのは、その使用方法、態様、目的等からみて、彼の俳優等としての評価、名声、印象等を毀損若しくは低下させるような場合、その他特段の事情が存する場合(例えば、自己の氏名や肖像を商品宣伝に利用させないことを信念としているような場合)に限定されるものというべきである。しかしながら、(中略)俳優等の氏名や肖像を商品等の宣伝に利用することにより、俳優等の社会的評価、名声、印象等が、その商品の宣伝、販売促進に望ましい効果を収め得る場合があるのであって、これを俳優等の側からみれば、俳優等は、自らかち得た名声の故に、自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有しているのである。ここでは、氏名や肖像が、(一)で述べたような人格的利益とは異質の、独立した経済的利益を有することになり(右利益は、当然に不法行為法によって保護されるべき利益である。)、俳優等は、その氏名や肖像の権限なき使用によって精神的苦痛を被らない場合でも、右経済的利益の侵害を理由として法的救済を受けられる場合が多いといわなければならない。
(三) まとめ
以上考察したところにより、原告マーク・レスターの主張する氏名権及び肖像権は、これを前記(一)及び(二)の前段で述べたような氏名及び肖像に関する人格的利益(以下において「氏名及び肖像に関する精神的利益」と称する。)と前記(二)の後段で述べたような経済的利益(以下において「氏名及び肖像に関する財産的利益」と称する。)に分類することができる。
おニャン子クラブ事件判決抜粋
- (東京地裁 H2.12.21判決 S61(ワ)12560号事件)
人は、自己の氏名、肖像を、自己の意思に反してみだりに使用されないことについて、法律上保護される人格的な利益を有しているものと解するのが相当である。もっとも、他人の氏名、肖像が使用される方法、目的、態様等が、社会的、公益的な観点から相当であると認められる限りにおいては、その使用行為が違法な侵害と見ることが相当でない場合も存し、また原告らのような芸能人の場合には、通常、その氏名、肖像が広く社会に公開されることを希望あるいは意欲しているのが一般であると解されるから、その意味で、他の一般的人とは、保護されるべき利益の範囲や程度に差異が生ずることもありうる。
被告の行為は、被告が、原告らの氏名及び肖像写真を表示したカレンダーを販売したというものであって、ここで原告らの氏名、肖像は、商品自体の重要な構成部分とされ、それがいわば売買取引の対象物にされているものと認められる。このような方法、態様による氏名、肖像の使用行為は、原告らのような立場のものであっても、到底承諾が推定されるものとはいえず他の観点からも違法性を欠く相当な行為であると認めることは困難である。そして、かかる人格的な利益は、原告ら各自固有の排他的なものであるから、これを害する行為に対する差止請求及び差止めを実効あらしめるため、右行為を組成する物の廃棄請求が認められるべきである。 - (東京高裁 H3.9.26判決 H2(ネ)4794号事件)
芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価値として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。したがって、右権利に基づきその侵害行為に対しては差止め及び侵害の防止を実効あらしめるために侵害物件の廃棄を求めることができるものと解するのが相当である。
(中略)
原判決は、被控訴人らの人格権に基づく差止請求等を認容している。しかし、前記のように被控訴人ら芸能人にあっては、その社会的評価の低下をもたらすような氏名・肖像の使用をされない限り、その人格的利益の毀損は発生しないものと解すべきところ、控訴人による被控訴人らの氏名・肖像の使用はいまだ人格的利益の毀損の域にまでは達していないものというべきであるから、原審が被控訴人らの人格権に基づく差止請求等を認容した点は失当といわざるを得ない。 - (最高裁 H4.10.23取下げ)
〈被告は、上告したが、程なく取下げた。〉
馬名のパブリシティ権を否定した
東京地裁判決の抜粋
(前略)
所有権は、有体物を客体とする権利であって、その作用は、有体物を物理的に占有支配する権能及びこれを円滑に行使するのに必要不可欠な権能(例えば、登記請求権等)にとどまる。物の所有者以外の第三者が、物に備わった顧客吸引力を利用する場合であっても、所有者の物に対する物理的な支配状態を妨げない限り、所有権が物について有する排他的な支配権と矛盾しないというべきであるから(最高裁昭和59年1月20日判決民集38巻1号1頁参照)、所有権の作用によって、物の顧客吸引力などの経済的価値を排他的に支配する権利を基礎付けることはできない。
(中略)
第三者が、他人の所有物を、所有者の承諾なく、物理的に毀損したような場合であっても、特段の事情の存しない限り、所有者の人格権を侵害することがないことは明らかである。これと同様に、第三者が、他人の所有に係る物について、所有者の承諾なく、その物が備える顧客吸引力を利用したとしても、所有者の人格権を侵害することにはならないことも明らかである。
(中略)
我が国において、物の名称等の使用等に関しては、著作権法、商標法、不正競争防止法などの知的財産権関係法が置かれ、それぞれの法律の立法趣旨に沿って、各法律が、所定の範囲の者に対して、所定の要件の下で、排他的な使用権(すなわち専有権)を付与している。
(中略)
各法律により、それぞれの権利の発生原因、内容、性質、範囲、消滅原因等が明確に規定されている所以は、そもそも、法律の制約がない限り、国民は私的活動の自由が保障されていること、また、排他的な権利は一般人の経済活動や文化活動の自由を抑制するものであり、取得原因、内容についての明確な規定を設けることなく排他的権利を付与することがあれば、国民の行動の自由を過度に制約するおそれが生じて、妥当でないことなどの理由によるものである。
このように、知的財産権関係法が付与する排他的権利は、その性質上、権利者に対して、独占的保護の限界を画したものと解されるべきであり、第三者に対して、行為の適法性の限界を画するものとして解されるべきものである。したがって、第三者が、知的財産権関係法の定める排他的権利の範囲に含まれない態様で行為をすることは、適法な行為というべきことになる。
(中略)
第三者が、他人の所有物について生じた経済的な価値を利用しようとする場合に、有償又は無償で、所有者の許諾を受ける実例が無いとはいえない。
しかし、一般に、排他的保護が及ばない場合であっても、紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行し、あるいは、より詳細な情報を所有者から得るなど、さまざまな目的で、利用者が許諾を受けることもあり得るのであるから、このような実例があるからといって、直ちに、「物から生ずる経済的利益を独占的に享受する」ことを承認する社会的な慣行が定着し、その慣行が長い間尊重され、慣習法にまで高められていたと認めることはできない。
キング・クリムゾン事件
東高判決抜粋
(前略)
このように著名人が有する氏名、肖像等のパブリシティ価値は一箇の財産的権利として保護されるべきものであるから、パブリシティ価値を無断で使用する行為はパブリシティ権を侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。
一方、著名人は、自らが大衆の強い関心の対象となる結果として、必然的にその人格、日常生活、日々の行動等を含めた全人格的事項がマスメディアや大衆等(以下「マスメディア等」という。)による紹介、批判、論評等(以下「紹介等」という。)の対象となることを免れない。また現代社会においては著名人が著名性を獲得するに当たってはマスメディア等による紹介等が大きく与って力となっていることを否定することができない。そしてマスメディア等による著名人の紹介等は本来言論、出版、報道の自由として保障されるものであり、加えて右のような点を考慮すると、著名人が自己に対するマスメディア等の批判を拒絶したり自らに関する情報を統制することは一定の制約の下にあるというべきであり、パブリシティ権の名の下にこれらを拒絶、統制することが不当なものとして許されない場合があり得る。
したがって、他人の氏名、肖像等の使用がパブリシティ権の侵害として不法行為を構成するか否かは、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等のパブリシティ価値に着目しその利用を目的とするものであるといえるか否かにより判断すべきものであると解される。
(中略)
本件書籍の発行の趣旨、目的、装丁、内容及びこれらに対する考察結果は、次のとおり
(中略)
本件書籍の中心的部分を占める作品紹介の部分に掲載されているジャケット写真187枚のうち被控訴人本人の肖像写真が使用されているものはわずか3枚で、これに「キング・クリムゾン」の構成員の肖像写真を加えてみても合計5枚にすぎない。そのほかの多くのジャケット写真は被控訴人又は「キング・クリムゾン」の構成員と直接関係しない独創的な図柄や絵画、写真等が使用されており、いずれの作品紹介にあってもジャケット写真の占める部分は当該紙面の4分の1未満に抑えられている上、作品概要と解説文が果たす役割の重要性も無視することができないから、ジャケット写真がその中心的な役割を果たしているということはできない(したがって、作品紹介の価値の源泉がジャケット写真にある旨の被控訴人の主張は採用できない。)。
(中略)
本件書籍は「キング・クリムゾン」及び被控訴人を含む音楽家について収集したその成育過程や活動内容等の情報を選択、整理し、その全作品を網羅した情報として愛好家に提供しようとするものであり、作品紹介が中心部分を占め、すべての作品についてジャケット写真が掲載されている。前記認定にかかる本件書籍の発行の趣旨、目的、書籍の体裁、作品紹介欄の構成等からすると、これらのジャケット写真は、被控訴人本人や「キング・クリムゾン」の構成員の肖像写真が使用されているものを含めて、いずれもが各レコード等を視覚面から表示するものとして掲載され、作品概要及び解説と相まって当該レコード等を読者に紹介し強く印象づける目的で使用されているものとみるべきであって、被控訴人本人や「キング・クリムゾン」の構成員を表示ないし印象づけることを主たる目的として使用されているとみることはできない。
(中略)
これに対し被控訴人は、本件書籍は被控訴人自身の顧客吸引力を利用するものである旨主張する。しかし、著名人の紹介等は必然的に当該著名人の顧客吸引力を反映することになり、紹介等から右顧客吸引力の影響を遮断することはできないから、著名人の顧客吸引力を利用する行為であるというためには、右行為が専ら著名人の顧客吸引力に着目しその経済的利益ないし価値を利用するものであることが必要であり、単に著名人の顧客吸引力を承知の上で紹介等をしたというだけでは当該著名人の顧客吸引力を利用したということはできない。
(中略)
写真を多用したからといって直ちにパブリシティ価値の利用を目的としていると断定することはできないから、多用する目的やジャケット写真以外の記述部分の内容等を全体的かつ客観的に観察して、これが専らパブリシティ価値に着目しその利用を目的としている行為といえるか否かを判断すべきものであり、本件書籍がこれに該当しないことは前記のとおりある。したがって、被控訴人の右主張は失当である。