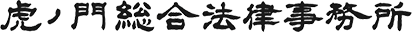慰謝料高額化傾向をどう捉えるか杉浦尚子
一 慰謝料とは?
慰謝料とは、財産以外の損害、つまりある者が受けた精神的あるいは肉体的苦痛に対する損害の賠償をいいます。
慰謝料請求の根拠となる条文は、民法七一〇条、民法七一一条二項です。七一〇条は「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず(略)損害賠償の責めに任する者は財産的損害以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す」と定めています。
二 慰謝料請求のできる場合
具体的に、どの様な場合に慰謝料の請求ができるのでしょうか。
左記に述べたように慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償ですから、精神的な苦痛を伴うような侵害行為があれば理論的には慰謝料の請求ができます。ある学者は、以下の様に法的利益を分類しこれらが侵害された場合に、慰謝料請求が認められると分類しています。
- 1) 生命
- 2) 身体
- 3) 自由(精神的自由・身体的自由)
- 4) 名誉・信用
- 5) 貞操
- 6) 生活妨害
- 7) 婚約
- 8)~14)(我妻栄、新訂債権総論)
例えば、交通事故の被害者は、1)、2)の生命や身体に対する侵害を受けたとして慰謝料を請求できます。第三者が出版した書籍に、3)の名誉を侵害するような記載があったとして、慰謝料を請求することができます。ロス疑惑について週刊誌に記載された三浦一義氏は、週刊誌発行者に対して数々の勝訴判決を得ています。6)の生活妨害といえば、最近では小田急線沿線住民が騒音妨害を根拠に、小田急電鉄に対して提訴した慰謝料請求訴訟がその例です。
三 慰謝料額の算出の仕方
慰謝料は、精神的苦痛や肉体的苦痛に対する損害の賠償ですから、ある者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛をいくらと見積もるかというのは、非常に難しい問題です。民法には慰謝料はこうして算出する、などという規定はありませんので、裁判官は広範な裁量の中で、事例毎の様々な事情を考慮して慰謝料額を決定します。例えば、離婚慰謝料に関する事例で仙台高等裁判所は、慰謝料の「額は、当事者双方の経歴、資産収入、婚姻の実体、離婚に至る経緯等諸般の事情を考慮すると…」と様々な事情を考慮して慰謝料額を二〇〇万円としました(S六一・一・三〇判決)。
ただ、慰謝料額が裁判官の裁量により左右されるといえども、類似の被害を負ったAさんとBさんの慰謝料額に天と地との開きがあるというのは、被害者間の公平の観点から妥当ではなく、裁判官をはじめとした法律家は多かれ少なかれ、類似事例を参考にするなど配慮をしています。また、交通事故については、昭和三四年ころの事故発生件数の増加に伴い、事件処理の迅速化、被害者間の公平が叫ばれ、定型的に慰謝料額が割り出される方式がとられています。
四 裁判例における慰謝料額の推移
裁判での慰謝料額は、法益の種別により程度の差はありますが概ね増加傾向にあるといえます。この慰謝料の高額化の傾向は、時間の経過と共に貨幣価値が下落し名目的な金額が大きくなったという原因のほかに、人格的利益に対する法的保護の必要性への人々の意識の高まりに対応していると考えられます。人格的利益に対する法的保護の拡大と強化は人類の歴史の必然的な発展方向であると主張する者もいます。
では、具体的に慰謝料はどのように推移しているのでしょうか。以下では、慰謝料請求が認められる事案の代表例である、交通事故の場合と離婚等身分関係の事案を検討します。
1 交通事故の場合
交通事故の慰謝料は、大きく1)死亡慰謝料(被害者が死亡した場合の被害者本人の精神的、肉体的苦痛に対する賠償)、2)傷害慰謝料(被害者が傷害を負った場合の精神的、肉体的苦痛に対する賠償)、3)後遺症慰謝料(被害者が後遺症傷害を負った場合の精神的、肉体的苦痛に対する賠償)に分けられます。この他に、被害者の遺族、親族の慰謝料が考えられますが、以下では1)~3)につきケースを選別して推移を検討していこうと思います。
1) 死亡慰謝料
(単位:万円)
| 被扶養者のある場合 | ||
|---|---|---|
| 昭49 | 600 | 800 |
| 一家の支柱 | 母親(妻) | その他 | |
|---|---|---|---|
| 昭60 | 2,000 | 1,600 | 1,500 |
| 平9 | 2,600 | 2,200 | 2,000 |
2) 傷害慰謝料(被害者が入院期間一ヶ月、及び通院期間一ヶ月の傷害を負った場合)
(単位:万円)
| 入院期間一ヶ月の場合 | 通院期間一ヶ月の場合 | |
|---|---|---|
| 昭49 | 15 | 7.5 |
| 昭60 | 26 | 14 |
| 平9 | 32 | 17 |
3) 後遺症慰謝料(後遺症等級数第一級、第八級、第一四級の場合)
(単位:万円)
| 第1級 | 第8級 | 第14級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 昭49 | 20歳位以下 | 1,000 | 336 | 37 |
| 上記以外 | 800 | 269 | ||
| 昭60 | 1,900 | 660 | 90 | |
| 平9 | 2,600 | 770 | 100 | |
注
1級とは
両目が失明したもの、咀嚼及び言語の機能を廃したもの、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの等をさします。
8級とは
1眼が失明し、又は1目の視力が0.02以下になったもの、脊柱に運動障害を残すもの、1手の親指を含み2の手指を失ったもの、1下肢を5センチメートル以上短縮したもの等をさします。
14級とは
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの、3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの、1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解する事ができない程度になったもの、1手の小指の用を廃したもの等をさします。
2 離婚等身分関係慰謝料の場合
離婚の際の慰謝料は、離婚原因慰謝料分(相手方の不貞行為、暴力等)と離婚自体による慰謝料分を合算されたものと考えられています。先ほど示した仙台高裁の判決のように離婚における慰謝料「額は、当事者双方の経歴、資産収入、婚姻の実体、離婚に至る経緯等諸般の事情を考慮すると…」と様々な事情を考慮して算出されます。
その中で、慰謝料算定の基準となる要素としては、婚姻期間、婚姻関係破綻への有責的行為(不貞行為、暴力等)、有責期間、離婚時の年齢、資力等があげられます。一般に婚姻期間、有責期間は長いほど、離婚時の年齢は高齢であるほど、慰謝料を請求される側の資力は高いほど、慰謝料額は多くなる傾向にあります。
このように、離婚慰謝料の算定では、様々な要素が事情として考慮されることから、交通事故の場合のように一定基準に照らして、慰謝料額の推移を検討するのは困難です。また、時折発表される、離婚慰謝料に関する資料もその基礎資料の統一されていないため、以下にあげるデーターは比較において不完全でありますが、一応の慰謝料額の推移を示す趣旨で、1)一定時期の裁判での離婚慰謝料の認容額、2)裁判で認容された離婚慰謝料の平均額、3)最も多い認容額の分布等を示させて頂きます。
(単位:万円)
| a 認容額 | b 平均額 | c 分布 | |
|---|---|---|---|
| 昭25~昭29 | 0.5~50 | 約 20 | 10~30 |
| 昭51~昭53 | 20~500 | 約 100 | 100~200 |
| 昭55~平1 | ?~1000 | 約 190 | 200~300 |
| 昭55~平6 (但し、公刊判例37件のみのデータによる) |
100~1500 | (約400) 但し、実際の平均額より相当高額と思われる |
300 |
昭和五一年から五三年の判決に関しての上記調査結果は、東京、大阪、名古屋の裁判所のみを対象としたものでありますが、当時慰謝料認容額は五〇〇万円どまりであり、その金額で頭打ちの傾向があるといわれていました(司法研究報告書第三二輯第一号)。が、昭和五五年には、慰謝料額一〇〇〇万円を認める判決が認容されました。
とはいえ、一〇〇〇万円を越える高額慰謝料額を認めた判例は、未だ数が少なく、稀なケースであると言えます。一〇〇〇万円を越える高額慰謝料を認めた裁判は、相手方が資産家である、婚姻期間が二〇年以上の長期の及ぶ、相手方に破綻の責任が明確である等それぞれに特色が見て取れます。
例えば、昭和五五・八・一の横浜地裁の判例では、夫に一〇〇〇万円の慰謝料の支払いをするよう命じましたが、この夫は会社社長であり、同居期間一〇年、別居期間一〇年の合計約二〇年間の婚姻期間があり、離婚原因が夫に四,五名の女性との別居前からの継続的肉体関係があったというケースです。
ただ、昭和五五年から平成元年のデータでも五〇〇万円を越える慰謝料を認容した判例は、四八〇件中八件(2.6パーセント)に過ぎません。が、具体的事案に応じて妥当な判断をするためには、これまでの先例にあまりとらわれないようにする(特に、上限であるかのように扱う必要はない、とする)という裁判所の姿勢が表われていると思います。
ただ、慰謝料は、人格的利益に対する保護の必要性の高まりに対応させて適正な金額を認め漸次増額することが望ましく性急に高額化を目指すべきではない(斉藤)、という意見にも留意しておきたいと思います。この意味で、慰謝料の高額化傾向は、慰謝料額の妥当な基準を模索する時代に入っていることの表われとしてみるべきであろうと思います。
空クレジット判決は空リース判決を変えるか(最高裁判所第一小法廷 平成14年7月11日判決、平成11年(受)602号)
1 空クレジットとは
まず、いわゆる「空クレジット」とは何かということであるが、これは、主債務者が販売店から商品を購入しないにも関わらず、販売店と共謀して(時にはクレジット会社とも共謀して)商品を購入するかのように見せかけ、クレジット会社との間で立替払契約を締結し、売買代金をクレジット会社から販売店に対して支払わせることである。
2 空クレジットの保証人への請求
このような場合、主債務者がクレジット会社に対する支払義務を履行する限り、特に大きな問題は生じ得ないが、「空クレジット」の手法を用いてまで金銭を得んとする主債務者である以上、資金繰りが苦しい者がほとんどであり、クレジット会社への支払義務が滞ることもしばしば見られるのが実態である。
このような場合、クレジット会社は同契約の連帯保証人に残金の請求を起こしてくることとなる。
3 空クレジットについての裁判例
保証人も保証契約当時に「空クレジット」であることを知っていたとすれば、上記のようなクレジット会社からの請求に対し、責任を免れ得ないことは当然であるが、これに対し、「空クレジット」であることは知らなかった場合にまで、保証人が責任を負わねばならないかという点が問題になるのである。
この点については、これまで多くの裁判例が出されていたが、それらはクレジット会社の請求を認めるものと、認めないものに判断が分かれており、結論は定まってはいなかった。
これらの裁判の中で保証人側の支払義務を免除させるべく、さまざまな理論構成がなされてきたが、その中心となるのは"錯誤無効"の主張である。
そして、保証人側のこの"錯誤無効"の主張に対し、空クレジットに関する"錯誤"を動機の錯誤に過ぎないと見るのか、要素の錯誤と見るのかということで、裁判所の結論が分かれてきたのである。
4 錯誤について
ここで、前提として錯誤とは何であるのか、また動機の錯誤、要素の錯誤とは何であるのかと言う点について、ごく簡単にではあるが触れておきたい。
まず、「錯誤」についてであるが、これは「効果意思(内心)と意思表示の齟齬」を指している。平易な言い方をするならば、"思い違い"または"言い間違い"のことである。
つまり、実際に行った意思表示と、内心で思っていた内容とが異なっていた場合には、これは錯誤となり、このような意思表示は原則無効となるのである(民法95条)。
ただし、錯誤があればいつでも保護されるというわけではなく、保護に値する錯誤であるべきだということから、「要素の錯誤」であることが求められている。
すなわち取引の相手方の保護という観点から、意思表示の要素(中心部分)につき錯誤がある場合に限って、無効の主張ができるということになっているのである。
次に、「動機の錯誤」であるが、これは意思表示を行うに至った「動機部分」について、思い違いがあった場合を指している。
なぜこのように「動機の錯誤」を他の錯誤と区別するのかと言うと、意思表示そのものについての言い間違い(例えば、代金を100万円だと考えて契約書を作ったが、表示上は1000万円としてしまった)と、意思表示を形成するに至った動機についての思い違い(例えば、すぐれた性能を有していると思って購入した物が、実際は低い性能しかなかった場合)とでは、質が異なるという考え方に基づいているのである。
なぜなら、意思表示を受ける相手方には、通常意思表示をした者の動機までは知ることはできないため、動機についての思い違いという場合には、動機が契約上表示されている場合にのみ、通常の錯誤と同様に無効の主張ができると解されているのである。
そして実際の契約においては、契約締結の動機まで表示することはきわめて少ないため、「動機の錯誤」の場合には、ほとんど保護されないこととなる。
5 クレジット契約の法的性質
以上の錯誤についての理解を前提に、これまでの裁判例がなぜ空クレジットをかたや動機の錯誤と捉え、かたや要素の錯誤だと捉えたのかというと、これはクレジット契約の法的性質の考え方が大きく影響していると思われる。
すなわち、クレジット契約をクレジット会社が金銭を貸与している面を中心にとらえると、クレジット契約の保証人とは金銭消費貸借の保証人と同視できるのであり、主債務者が支払義務を負うこと、またこの債務について保証するとの認識が明確にある以上、意思表示そのものには特に錯誤はない。あるとすれば、主債務についての担保の有無(購入する商品は不払いが起きた場合には主債務の担保となるため)についての錯誤であり、これは動機の錯誤に過ぎないと解されるのである。
これに対し、クレジット契約というのは、売買契約との密接不可分の契約だととらえると、クレジット契約の保証人というのは、金銭消費貸借の保証人とは全く異なる立場にあるのであり、主債務の前提となる売買契約の成否についての思い違いは、保証契約の重要な内容についての錯誤になると解されるのである。
6 空クレジットについての最高裁判決
以上の大きく見て2つの考え方により、空クレジットの際の保証人の責任は裁判例が分かれていたわけであるが、最高裁判所第一小法廷は、平成14年7月11日、「保証契約は、特定の主債務を保証する契約であるから、主債務が、商品を購入する者がその代金の立替払いを依頼しその立替金を分割して支払う立替払契約上の債務である場合には、商品の売買契約の成立が立替払契約の前提となるから、商品売買契約の成否は、原則として、保証契約の重要な内容であると解するのが相当である。」とし、また保証人が空クレジットであることを知らずに保証契約を締結した場合、保証人のその意思表示は「法律行為の要素に錯誤があったものというべき」だと判示し、保証人の錯誤は、要素の錯誤にあたることを明確にして、保証人には責任がないとの判断を示したのである。
また、同判決は、その実質的な理由づけとして、クレジット契約の経済的な実質は金融上の便宜供与にあることは認めながらも、正規のクレジットと空クレジットでは、主債務者の信用に実際上の差があることは否定できないとし、また保証人としては主債務者がどちらの態様のものであるかによって、負うべきリスクが異なってくるはずであり、看過し得ない重要な相違があるといわざるをえないと判示している。
7 空リースとは
以上の「空クレジット」に対し、いわゆる「空リース」とは、主債務者が販売店と共謀して(時にはリース会社とも共謀して)、販売店から商品を受領するかのように見せかけ、主債務者はリース会社との間でリース契約を締結し、また、リース会社と販売店の間で売買契約を締結させ、売買代金をリース会社から販売店に対して支払わせることである。
8 空リースの保証人への請求
空リースの場合にも、主債務者の支払が滞った場合には、当然リース会社から保証人へ請求がなされることとなるが、保証人が空リースであることを知らずに保証した場合にリース会社の保証人に対する請求が認められるのかどうかについて、空クレジットの場合と同様、これまでの裁判例は"動機の錯誤"か"要素の錯誤"か、で結論が分かれてきたのである。
9 リース契約の法的性質
なぜ、これまでの裁判例が空リースについて動機の錯誤か要素の錯誤かいう判断の違いが出てきているのかといえば、これもクレジットの場合と同様に、そもそものリース契約についての法的性質の捉え方が大きく影響していると思われる。
つまり、リース契約をリース会社が金銭を貸与している面を中心にとらえると、リース契約の保証人とは金銭消費貸借の保証人と同視できるのであり、主債務者が支払義務を負うこと、またこの債務について保証するとの認識が明確にあれば、契約の要素について錯誤がないこととなるのであり、空リースかどうかは"動機の錯誤"と考えられるのである。
これに対し、リース契約を売買契約との密接不可分の契約だととらえる等、金銭の貸与とは別個の性質もふまえてとらえるならば、リース契約の保証人というのは、主債務の前提となる売買契約等の成否についての思い違いは、保証契約の重要な内容についての錯誤になると解されるのである。
10 空クレジットについての最高裁判決の射程範囲
それでは空クレジットについての上記の最高裁判決は、空リースの保証債務にも影響を及ぼすであろうか。
この点、即断が許されないことは言うまでもないところであるが、私見としては、この度の判決は、同様の法的関係にある空リースの保証人への請求にまで射程が及んでおり、空リースの場合も保証人の債務は免れ得る性質のものだと考える。
その理由としては以下の3点が挙げられよう。
(a)そもそもクレジット契約とリース契約は、法律構成の差はあれ、販売店から購入したい商品があるが購入資金がないという場合に、当該商品代金をクレジット会社またはリース会社が販売店に支払い、クレジット会社またはリース会社は当該商品の使用を主債務者に認めつつ、同商品を担保として、当該代金相当額に利息等を付した額を分割で回収するというものであり、その実体は両契約いずれであっても変わるところがない。
(b)また、空クレジットにおける最高裁判決は「保証債務は、特定の主債務を保証する契約であるから、主債務がいかなるものであるかは、保証契約の重要な内容である。」と判示しているが、これは文言上も、その内容からも広く保証債務一般についての説示だと考えられるのであり、空リースの保証の場合にも当然該当すると思われる。
(c)さらに、同判決の実質的な理由づけとして挙げられている点、すなわち、クレジット契約の経済的な実質は金融上の便宜供与であるが、正規のクレジットと空クレジットでは、主債務者の信用に実際上の差があることは否定できないこと、また保証人としては主債務者がどちらの態様のものであるかによって、負うべきリスクが異なってくるはずであり、看過し得ない重要な相違があるといわざるをえないという各点も、リース契約においてそのままあてはまることは明白である。
したがって、上記最高裁判決の文言から見ても(b)、同判決の実質的な理由付けから見ても(c)、さらにはクレジット契約とリース契約の経済的実体の類似性から見ても(a)、上記最高裁判決は、空リースの保証債務にまでその射程距離が及んでいるものと考えられ、空リースであることを知らずに保証契約を締結した保証人は、当該保証債務を負担することはないと解すべきである。
(文責:吉田朋)
以上
「パブリシティ権法」(仮称)の立法を呼びかける北村行夫
日本における「パブリシティ権」、すなわち他人の氏名や肖像の商業的な利用に関しては、有名なマーク・レスター事件判決(東京地裁 昭和51年6月29日判決)を嚆矢として、その後の多くの判例が、パブリシティ権を「法的利益として認めている」と一応いえる。
しかし、一連のパブリシティ権判決を支えているのは、不法行為法理である。その背後にあるのは、民法709条の「他人の権利」の意義を、「権利」に限定せず、「法的に保護すべき他人の利益」と解釈する司法判断に依存するものであり、これによって切り開かれた地平に、「保護されるべき法的利益」の一つとしてパブリシティ権が許容されているのである。
したがって、ここに「法的利益として認められている」という場合、所有権や特許権、あるいは著作権が法的権利として認められているということとは明らかに質的な差異を有する。すなわち、パブリシティ権が、法的に認められているという意味は、より正確に言えば、不法行為法の領域で、司法の場において法的な保護の対象と認められているというにすぎないのである。
もとより、司法の場において認められるということは、裁判の場面でしか保護されないと言うことを意味するものではない。裁判所によって保護されているという事実は、この「法的利益」を無視すれば結局は裁判の場に引きずり出され、不法行為として弾劾され、損害賠償等の責任を課されると言う事実を予測させ、かかる結果が予測できる以上、取引社会においてもパブリシティを権利同然に承認して取り扱わざるをえない、こういう現実が確立されてきていることを意味する。このことは、周知のとおりである。この状態を指して、私達は一応「権利」と呼んでいる。
しかし、これは、一種のパラドックスである。なぜなら、この「権利」は、不法行為法理の進化によって、その保護対象が権利以外の「法的利益」へと拡げられたがゆえに保護される「権利」だからである。言い換えれば、取り引き法理の中では「権利として」存在しないが、不法行為法理を睨むと守られるべき利益として存するが故に、取り引き社会にあっても「権利」の様に扱われるというのが、パブリシティの「権利」の実情である。
しかし、「俳優等は、自らかち得た名声の故に、自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専属的に利用させうる利益を有している」とする判例(マーク・レスター判決他)を見るまでもなく、パブリシティの現実からすれば、この「権利」は、本格的にメディアの発達した取り引き社会を前提に機能する排他独占的な利益であるから、商標権者にとっての商標を保護する必要性にも似ている。すなわち、パブリシティ価値を有する者にとっては、ますます積極的に活用すべき財産として認識されるようになってゆく「利益」であるといえよう。
ところが、その利益の範囲について、これまでの判例が全て明確にしているとはいえないし、すべての解明を判例に期待するのも過大な要求である。なぜなら、裁判は、個別事案の解決に必要な限度で、解決に必要な角度からこの利益に光を照らすにすぎないからである。むしろ判例上は、権利の定義はともかく、性質も、差止請求権肯否やその根拠も、必ずしも一貫しているわけではないし、まして、相続性の有無や存続期間に至っては、判例からは不明である。
そこで、パブリシティ価値を有する者が、この「法的利益」を「権利」として認める相手方との間で自由に契約内容を決めるという方法がさしあたり考えられる。が、それによって、この問題が解決できるわけではない。例えば、当事者の契約によって、権利者の死後に至る時機まで権利が存続する旨を定めていても、権利者の死後までパブリシティ権が存続し得ないものだとの判決が出れば、権利者の死亡によって誰でも自由に利用できることとなるのに対し、苦労して契約した相手方は、契約に拘束される結果として、契約に及んでない者よりも無用な負担を負い続けることになりかねない。さりとて、判決後は契約の効力を、失効させるということが契約解釈上当然に可能かとなると疑問があるのみならず、仮にそのようにしても、死亡=失効後に頭金ないし契約金を精算すべきか否かという問題に直面する可能性がある。なぜなら、通常それらのライセンス契約では、支払い済み金員は不返還とする旨の特約が付せられているので、同特約の効力を巡る争いが問題を一層複雑化させると予想されるからである。
つまり、二つの方向から、パブリシティ権の立法化が要請されている。
一つは、その性質上、パブリシティ権は、プライバシー権と違って、侵害された場合に事後的に、あるいは受働的にないしは侵害されうる場合に予防的に機能すれば足るというようなものではない。むしろ権利者にとって、それを財産的に積極的に活用しうることを常態とする法的利益であり、またそれを使用したい者にとっては許諾をえて適法な使用をしたいものである。その点からすると、パブリシティが権利たることを明定し、その内実・範囲を明確にして、文字どおりの権利性を付与すべきことが求められているのである。
もう一つの要請は、パブリシティ権が、表現の自由と境界を接しているからである。より立ち入って言えば、パブリシティ権の構成要素である氏名や肖像は、本人による使用はもとより、その「指称機能」にもとづいて、本来的に他人による使用を予定するものと言わざるをえない。そうであれば、それが氏名や肖像の他人による使用を前提とし、全てではなくいわゆる商業的使用となったときに限って権利として機能することとするなど、その境界線についての明確な線引きをしなければ、表現の自由の保護を困難とする場合を生じかねないのである。特にこの点は、情報化社会における表現の自由とその制限という観点から重要性を増しているのである。
(以下、試案略)
以上
顧客吸引力理論の破綻とパブリシティ権理論の再構築北村行夫
第1 はじめに
第2 パブリシティ権概念の「輸入」と顧客吸引力理論の展開
1 顧客吸引力理論の公理のような是認という現状
2 アメリカにおけるパブリシティ権確立のプロセス
(1890 プライバシー権 ウォーレン判事、ブランダイス判事の提唱)
- 1902 Roberson事件(ニューヨーク上訴裁判所 消極)
- 1903 N.Y.州プライバシー法 の制定(現在のN.Y市民権法)
- 1905 Pavesich事件(ジョージア州最高裁 積極)
史上初の実質的なパブリシティ事件
プライバシー権(人格権)を根拠にして認容 - 1941 O'Brien事件(第5巡回控訴裁判所 消極)
セレブリティ=著名なプロフットボール選手の初登場とそれゆえのプライバシー権の否定
しかし、認容すべしとのホームズ判事の強い反対意見 - 1953 Healan判決(第2巡回控訴裁判所 積極)
史上初のパブリシティ権の宣言(フランク判事)
プロ野球選手の肖像を野球カードに利用
プライバシー権から独立した新しい権利とし、その性格も財産権とした
(1954 ニンマー教授「パブリシティ権」論文発表)
3 アメリカにおけるパブリシティ権確立過程の要点
- 氏名・肖像の利用権とプレスの自由権との相克への注目(Roberson判決参照)
- 両権利の境界を客観化する努力
- プライバシー権における「私事」性の確立とパブリシティ権の分岐
- アメリカ的プラグマティズムに基づくパブリシティ権概念の確立
4 日本におけるパブリシティ権の展開
- 1976 マークレスター事件(S51.6.29 東京地判決)
肖像(映画の一シーン)のCFへの使用。
パブリシティ権の言葉はないが、日本最初のパブリシティ権判決。
パブリシティ権を財産権として構成。差止請求権は認めていない。
財産権の根拠付けに、顧客吸引力論の萌芽が見られる。
(人格権に基づく慰謝料を認めるが、マークレスターが二重契約をするような人物と誤解された精神的打撃に対するものであって、パブリシティ権としての慰謝料ではない。) - 1990 おニャン子クラブ事件2(H2.12.21 東京地判決)
氏名・肖像写真をカレンダーに無断使用。
パブリシティ権を人格権かつ財産権であると構成。
人格権侵害を根拠に差止、廃棄請求権及び慰謝料10万円を認めた(請求は、慰謝料100万円)。
財産権の関係では、慰謝料を下回るので、慰謝料。 - 1991 おニャン子クラブ事件3(H3.9.26 東京高判決)
パブリシティ権を顧客吸引力=財産権として構成し、且つ上記財産権を実行あらしめるため、差止・廃棄請求を認めるとした。なお、財産権侵害による損害は、15万円と認定したが、原審認容の限度10万円で認めるとしている。
5 日本におけるパブリシティ権確立過程の特質
- セレブの時代にセレブの事件として蓄積
- プレスの自由の問題意識が欠落
- 物のパブリシティ権の否定の根拠の探求が不徹底
- 有名人のみの権利?
- 機能にすぎない顧客吸引力を権利性の根拠へと昇格
6 顧客吸引力理論の外延における躓き(判例による物のパブリシティ権の否定)
- かえでの木事件(東京地H14.7.3判決 消極)
原告は、パブリシティ権類似の権利主張を、所有権に基づくものと釈明。 - 馬名のパブリシティ事件(名地H12.1.19判決 積極)
原告は、パブリシティ権類似の権利主張を、所有権以外に基づくものと釈明。
以下二つの事件も同じ構成。 - 馬名のパブリシティ事件(名高H13.3.8判決 積極)
- 馬名のパブリシティ事件(東地H13.8.27判決 消極)
- 物のパブリシティ権成立の余地の有無
第3 顧客吸引力理論の破綻と批判的克服
1 氏名・肖像の情報としての特性
- 表章情報
(a)氏名(肖像)の位置
「氏名は、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴である。」
(最判S.63.2.16「NHK日本語読み」事件)
(b)他人による利用の予定
標章と個人属性を結びつけることにより、本人の個性すなわち本人と他者との識別可能性が増大 - 表章情報から識別情報へ 【別紙6】略
2 顧客吸引力理論は、プレスの自由を脅かす
- 顧客吸引力は、個人の属性(特に有名人にあっては、通有性)の一つである。
- 有名人に対する言及にもパブリシティ権の網をかぶせてしまう。
- パブリシティ権の主張・立証責任ないしは抗弁責任
- 過渡期の判決としてのキング・クリムゾン事件判決
3パブリシティ権は、人格権を本質とする。
- 判例におけるパブリシティと人格権との関係
(a)マークレスター
(b)おニャン子一審
(c)おニャン子二審 - プライバシー権の縮減とパブリシティ権は無関係
- 人格権の内容は、推奨説によるべきである
自己の標章と自己の個人属性(企業等団体や個人、あるいは商品・サービスに対する好みや、選別の基準等)とを結びつけ、これを公表することは、人格の発露ないし個性を公にすることであり、本人の存在価値を左右するものであるから本人の人格権に関わる。
4 パブリシティ権は財産権でもある
- おニャン子一審判決との違い
- お金の支払は、対世効力の成立を説明できない
馬名のパブリシティ権東京地裁判決参照 - 人格権から転化した財産権である。
人格権と財産権は二者択一関係にはない。
本人にとって人格価値である氏名や肖像が、他人にとって使用価値あるものであれば、氏名や肖像はその他人にとっては財産性を有する。
以上