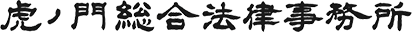「キング・クリムゾン事件」
(東京高裁平成11年2月24日判決、(ネ)第673号損害賠償等請求事件)
第一 事案の概要
1、当事者
控訴人(原審被告)エフエム東京は、FM放送を業とする会社であり、関連業務として出版活動を行っている。
被控訴人(原審原告)ロバート・フリップは、英国の著名なロックバンド「キング・クリムゾン」の一員である。
2、紛争の経緯
控訴人は、「地球音楽ライブラリー」という音楽に関するシリーズもの出版物にイギリスの著名なロックグループ「キング・クリムゾン」に関する書籍を編集し、出版した。
これに対し、同グループの創立期からのメンバーである被控訴人は、同書籍への自己の名称・肖像の利用は、同人のパブリシティ権を侵害したものであると主張して提訴した。原審東京地裁は、原告の請求を認め、書籍の廃棄等と損害賠償の請求を認めた(東京地裁平成10年1月21日判決、平成8年(ワ)第11327号事件)。
そこで、被告エフエム東京が控訴した。
3、本件控訴審判決は、原審を覆し、控訴人エフエム東京を勝訴とする逆転判決となった。
そこで被控訴人ロバート・フリップは上告した(最高裁平成11年(オ)第805号事件)が、最高裁は、平成12年11月9日上告棄却の決定を下し、判決は確定した。
第二 本判決の要旨
1、パブリシティ権とは何か。
「著名人がその氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人識別情報の有する経済的利益ないし価値(以下『パブリシティ価値』という。)を排他的に支配する権利」である(東京高裁判決書、以下たんに「高裁判決」という、6頁)
これは、一般に認められている「パブリシティ権の定義」である。
2、著名人の氏名・肖像の経済的利益ないし価値の本質は。
「固有の名声、社会的評価、知名度等を獲得した著名人の氏名、肖像等を商品の宣伝、広告に利用し、あるいは商品そのものに付する等により当該商品の販売促進に有益な効果がもたらされることは一般によく知られている。これは著名人に対して大衆が抱く関心や好感、憧憬、崇敬等の感情が当該著名人を表示する氏名、肖像等に波及し、ひいては当該著名人の氏名、肖像等と関連づけられた商品に対する関心や所有願望として大衆を当該商品に向けて吸引する力を発揮してその販売促進に効果をもたらす結果であると理解することができる。その結果、著名人の氏名、肖像等は当該著名人を象徴する個人識別情報としてそれ自体が顧客吸引力を持つようになり、一箇の独立した経済的利益ないし価値を具有することになる。」(高裁判決5~6頁)
これを、著名人が有する通有の機能としてみるか、パブリシティー権の本質と見るかは、見解の分かれるところであり、後者のように考えることを、顧客吸引力理論(以下、「吸引力理論」という。)と呼ぶ。
3、著名人の氏名・肖像の経済的価値ないし利益を同人の権利といえるか。
「このような著名人の氏名、肖像等が持つ経済的利益ないし価値は著名人自身の名声、社会的評価、知名度等から派生するものということができるから、著名人がこの経済的利益ないし価値を自己に帰属する固有の利益ないし権利として考え、他人の不当な使用を排除する排他的な支配権を主張することは正当な欲求であり、このような経済的利益ないし価値は、現行法上これを権利として認める規定は存しないものの、財産的な利益ないし権利として保護されるべきものであると考えられる。」(高裁判決6頁)
4、パブリシティ権侵害は、不法行為を構成するか。
「著名人が有する氏名、肖像等のパブリシティ価値は一箇の財産的権利として保護されるべきものであるから、パブリシティ価値を無断で使用する行為はパブリシティ権を侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。」(高裁判決7頁)
念のためにいえば、権利に限らず、法的に保護されるべき利益であれば、その侵害は不法行為となる。以上、いずれも通説的に認められているところである。
5、本判決の意義は、著名人の氏名や肖像に「顧客吸引力機能」を認めつつも、著名人の氏名・肖像等を内容とする行為の全てをパブリシティ価値の利用とはせず、従来から言われていた吸引力の理論に限界があることを明確にした点にある。
すなわち、判決は、次のように指摘する。
「一方、著名人は、自らが大衆の強い関心の対象となる結果として、必然的にその人格、日常生活、日々の行動等を含めた全人格的事項がマスメディアや大衆等(以下『マスメデイア』という。)による紹介、批判、論評等(以下『紹介等』という。)の対象となることを免れない。また現代社会においては著名人が著名性を獲得するに当たってはマスメディア等による紹介等が大きく与って力となっていることを否定することができない。そしてマスメディア等による著名人の紹介等は本来言論、出版、報道の自由として保障されるものであり、加えて右のような点を考慮すると、著名人が自己に対するマスメディア等の批判を拒絶したり自らに関する情報を統制することは一定の制約の下にあるというべきであり、パブリシティ権の名の下にこれらを拒絶、統制することが不当なものとして許されない場合があり得る。」(高裁判決7~8頁)
6、その結果、本判決は、著名人の氏名・肖像等の利用が、パブリシティ権の侵害になる場合とそうでない場合とがありうるとする。本判決の核心部分である。
「著名人の紹介等は必然的に当該著名人の顧客吸引力を反映することになり、紹介等から右顧客吸引力の影響を遮断することはできないから、著名人の顧客吸引力を利用する行為であるというためには、右行為が専ら著名人の顧客吸引力に着目しその経済的利益ないし価値を利用するものであることが必要であり、単に著名人の顧客吸引力を承知の上で紹介等をしたというだけでは当該著名人の顧客吸引力を利用したということはできない。」(高裁判決21~22頁)
「本件書籍は『キング・クリムゾン』及び被控訴人を含む音楽家について収集した成育過程や活動内容等の情報を選択、整理し、その全作品を網羅した情報として愛好家に提供しようとするものであり、内容的にみても紹介等の実質を備えていることが認められるから、本件書籍が被控訴人自身の顧客吸引力に着目しその経済的利益ないし価値の利用を目的として発行されたものとみることはできない。確かに本件書籍はほかの海外ロック・ミュージシャンの作品紹介書(甲第三ないし第六号証)と比較して肖像写真やジャケット写真の占める比重が大きいことが認められるが、ジャケット写真を多用するか否かは、書籍の価格、紙質、体裁等を含む全体的な編集方針にかかる問題であり、写真を多用したからといって直ちにパブリシティ価値の利用を目的としていると断定することはできないから、多用する目的やジャケット写真以外の記述部分の内容等を全体的かつ客観的に観察して、これが専らパブリシティ価値に着目しその利用を目的としている行為といえるか否かを判断すべきものであり、本件書籍がこれに該当しないことは前記の通りである。したがって、被控訴人の右主張は失当である。」(高裁判決22~23頁)
7、その判断の基準について次のようにいう。
「他人の氏名、肖像等の使用がパブリシティ権の侵害として不法行為を構成するか否かは、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等のパブリシティ価値に着目しその利用を目的とするものであるといえるか否かにより判断すべきものであると解される。」(高裁判決8頁)
8、本判決は、本件書籍についての事実認定ないし評価は、次のとおりである。
(1)題号、表紙、裏表紙、背表紙
「本件書籍は、題号に、世界的に著名なロック・グループである『キング・クリムゾン』のグループ名そのものが使用され、表紙、裏表紙及び背表紙には、『キング・クリムゾン』『KING CRIMSON』の文字が大書され、同グループの著名なジャケット写真がデザインとして用いられており、『キング・クリムゾン』の名称やジャケット写真によって『キング・クリムゾン』に関する書籍であることを購入者の視覚に訴え印象づける装丁になっていることが明らかである。」(高裁判決13~14頁)
(2)内容面
「本件書籍のうち12頁を占める伝記部分には、被控訴人を含む『キング・クリムゾン』の構成員の肖像写真五枚が掲載され、各作品紹介の扉部分のうち4頁に『キング・クリムゾン』の構成員及び被控訴人個人の肖像写真が掲載されていることからすると、右部分においても『キング・クリムゾン』の構成員及び被控訴人の肖像写真を利用して購入者の視覚に訴える体裁になっていることが認められる。」(高裁判決14~15頁)
(3)書籍の回収
「控訴人会社が出版する『地球音楽ライブラリー』シリーズは、ロック、フォーク等若者が愛好する現代音楽の各ジャンルの一流音楽家の作品を網羅し、その魅力と軌跡を解明することを編集目的としており、音楽家の成育過程や活動を年代順に説明する伝記、各書の中心部分となる作品紹介、及び人名索引から構成され、本件書籍以外にも、エリック・クラプトン、レッド・ツェッペリン、吉田拓郎、加山雄三等の音楽家を対象とする書籍が同シリーズとして出版されている。
本件書籍もこのような編集目的に従って編集されており、まず前書きにおいて本件書籍が『激しい離散と集合を繰り返しながらも、ブリティッシュ・ロック・シーンに豊饒な一大人脈を築き上げた彼らの軌跡を、グループとしてのアルバムはもとより、個々のメンバーがかかわった作品をも俯瞰することによって、余すところなく再現した一冊である。』と記載して本件書籍の目的と性格を明らかにした上、続く伝記の部分では、キング・クリムゾンの音楽活動を年代順に初期から『キング・クリムゾンの胎動』、『第一期キング・クリムゾン』、『第二期キング・クリムゾン』、『キング・クリムゾン空白の時代』、『Disciplineの時代』、『再びキング・クリムゾン空白の時代』及び『クリムゾン再生』に区分し、それぞれについて分析と解説を加えている。そして本件書籍の中心部分となる作品紹介では、アーティスト名、タイトル名、オリジナルレコード番号/CD(日本盤)番号、発売年、曲名、演奏者、プロデュース(以下『作品概要』という。)のほか、作品の時代背景、意義、特徴やエピソード等が解説担当者の専門的知識と情報を踏まえた分析及び評価等を交えて紹介されており、重要と思われる作品は見開きの片頁をジャケット写真と作品概要に当てもう一方の片頁を作品の紹介に当てており、そのほかの作品は作品の重要度に応じて一頁の紙面を上下に二ないし三分してそれぞれ紹介をしている。いずれもジャケット写真は当該作品紹介に使用される紙面の四分の一未満に抑えられている。」(高裁判決10~13頁)
なお、この点は原判決を変更するにあたり、裁判所が新たに付加した判示部分である。
9、そして、次のように結論付けている。
「以上を総合してみると、本件書籍に多数掲載されたジャケット写真は、それぞれのレコード等を視覚的に表示するものとして掲載され、作品概要及び解説と相まって当該レコード等を読者に紹介し強く印象づける目的で使用されているのであるから、被控訴人本人や『キング・クリムゾン』の構成員の氏名や肖像写真が使用されていないのはもちろんのこと、これが使用されているもの(これがわずかであることは前記の通りである。)であっても、氏名や肖像のパブリシティ価値を利用することを目的とするものであるということはできない。」(高裁判決19頁)
(抜粋の文責:北村行夫)
以上
「交通標語の著作物性と著作権侵害」
(東京地裁平成13年5月30日判決、東京地裁平成13年(ワ)第2176号 損害賠償請求事件)
第一 事案の概要
1、当事者と紛争の要旨
原告は「ボク安心、ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」というスローガン(以下「原告スローガン」という。)を創作し、財団法人全日本交通安全協会が主催した平成6年秋の全国安全スローガン募集に応募し、優秀賞に選定され、平成6年12月1日付の毎日新聞第1面に掲載された。
被告社団法人日本損害保険協会は平成9年度後半の交通事故防止キャンペーンとして、チャイルドシート装着を訴えるための啓発及び宣伝をするため被告株式会社電通にその宣伝の依頼をし、被告電通は、「ママの胸よりチャイルドシート」というスローガン(以下「被告スローガン」という。)を作成し、被告らは協議の上、前記宣伝として被告スローガンを各テレビ局に放送させた。
原告は、被告スローガンは原告スローガンの複製だとして原告の被った損害18億9000万円の一部である5000万円の損害賠償の請求をした。
2、争点
(1) 原告スローガンの著作物性の有無。
(2) 被告は原告スローガンの著作権(複製権)を侵害しているか。
第二 判旨
1、原告スローガンの著作物性の有無について
「著作権法による保護の対象となる著作物は『思想または感情を創作的に表現したものである』ことが必要である。『創作的に表現したもの』というためには、当該作品が、厳密な意味で、独創性の発揮されたものであることまでは求められないが、作成者の何らかの個性が表現されたものであることが必要である。文章表現による作品において、ごく短く、又は表現に制約があって、他の表現がおよそ想定できない場合や、表現が平凡で、ありふれたものである場合には、筆者の個性が現れていないものとして、創作的に表現したものということはできない。」…「原告スローガンは、3句構成からなる5・7・5(正確な字数は6字、7字、8字)調を用いて、リズミカルに表現されていること、「ボク安心」という語が冒頭に配置され、幼児の視点から見て安心できるとの印象、雰囲気が表現されていること、「ボク」や「ママ」という語が、対句的に用いられ、家庭的なほのぼのとした車内の情景が効果的かつ的確に描かれていることなどの点に照らすならば、筆者の個性が十分に発揮されたものということができる。したがって、原告スローガンは、著作物性を肯定することができる。
2、複製権侵害について
「両スローガンは、「ママの」「より」「チャイルドシート」の語が共通する。上記共通点については、両スローガンとも、チャイルドシート着用普及というテーマで制作されたものであるから、「チャイルドシート」という語が用いられることはごく普通であること、また車内で母親が幼児を抱くことに比べてチャイルドシートを着用することが安全であることを伝える趣旨からは、「ママの より」という語が用いられることもごく普通ということができ、原告スローガンの創作性のある点が共通すると解することはできない。これに対し、原告スローガンは、被告スローガンと対比して(1)「ボク安心」の語句があること、(2)前者が「膝」であるのに対し、後者は「胸」であること、(3)前者は、6字、7字、8字の合計21字が3句で構成されているのに対し、後者は、7字、8字の合計15字が2句で構成されている点において相違する。そして(1)原告スローガンにおいては「ボク安心」という語句が加わっていることにより、子供の視点から見た安心感や車内のほのぼのとした情景が表現されているという特徴があるのに対し、被告スローガンにおいては、3区構成からなる5・7・5調が用いられ、全体として、リズミカル、かつ、ゆったりした印象を与えるのに対し、被告スローガンにおいては、2句構成からなる7・5調が用いられ、きわめて簡潔で、やや事務的な印象を与えること等から、前記各相違は、決して仔細なものではなく、いずれも原告スローガンの創作性を根拠付ける部分における相違といえる。そうすると、両者は、前記の共通点があっても、なお実質的に同一のものということはできない。」として複製権侵害を否定した。
(抜粋の文責:中島龍生)
以上
「不倫殺人高裁破棄自判事件」(東京高裁平成7年12月4日判決、東京高裁平成7年(う)1228号殺人被告事件)
第一 事案の概要
1 事実関係
本件殺人事件の被告人は、殺人実行後暫らくして我にかえり、犯行の約10分後自首すべく自分の車にのって犯行現場近くの交番に赴いたが、警察官が不在であった。そこで、同交番入口付近に設置してある「不在派出所要緊急通報装置」であるインターホンを押した。しかし、被告人が犯行後興奮していたこと、繰作に不慣れであったことなどのため何回か通話を試みるも通話するに至らなかった。警察署には、このインターホン経由でかかってきて通話できなかった通報の時刻がおよそ午前6時45分ころとの記録がある。
そこで被告人は、公衆電話を使って警察に通報しようと考え、同じ町内にある公衆電話に移動して110番通報をし、自己の名前と居場所と自らの犯した犯罪事実を申告した。この時刻が午前6時55分であった。
ところが、こうしているうちに、犯行の目撃者である被告人の妻も、犯行目撃後まもなくして110番通報し、警察に犯罪事実を申告した。この時刻が、午前6時53分であった。
その結果、被告人が申告を開始した時刻は、目撃者による申告よりも、10分前であったにもかかわらず、被告人自身による犯罪事実の申告の完了は、目撃者による申告よりも2分遅れた。
2 争点
被告人は、自首したと言えるか。
すなわち、「未だ官に発覚せざる前」(刑法42条1項)(平成7年度改正後の条文では、「捜査機関に発覚する前」)に自己の犯罪事実を官に申告すると言うのは、申告の完了時点と第三者による申告時点とを機械的に比較することか、申告を開始した時点と申告完了までの諸事情を総合勘案して決すべきか。
第二 本判決の要旨
- 争点に対する判断
自首の成立を肯定した。 - 判旨
(1)高裁判決は、原判決が自首を認めなかった理由を以下のように推測する。
「以上の事実によれば、被告人が現実に自己の犯罪事実を警察官に申告した時点においては、すでに被告人の妻からの110番通報が茨城県警察本部通信司令室で受理されており、すでに捜査機関に被告人の犯罪事実が発覚しているものといわざるを得ないのであるから、右の時点を基準とする限り、被告人の右の通報をもって、刑法上の自首と認める余地はないとも考えられ、原判決もこの点を根拠に自首の成立を否定したものと推測される。」
(2)しかし、このように解することは、妥当な解釈ではないとして、自首規定の趣旨を以下のように述べる。
設けられたものであり、犯人の行為が自首に当たるかどうかは、右規定の趣旨から実質的かつ全体的に、時間的にもある程度幅をもって解釈されるべきであり、単なる時間的先後関係だけに拘泥することは同項の妥当な解釈とはいい難い(なお、改正刑法草案四九条一項参照)。」
(3)ここにいう実質的かつ全体的、あるいは時間的にある巾をもって解釈するとはどう言う基準によるべきかについて、以下のように述べている。
「犯人がいまだ捜査機関に自己の犯罪事実が発覚する前に、自ら自己の犯罪事実を申告して身柄の処分をゆだねる意図で捜査機関に出頭しておれば、捜査員不在等の事由により犯人が右の申告をすることができず、その間に犯人の申告以外の理由により、その犯人の犯罪事実が発覚したとしても、その接着する時間内に、犯人において自ら自己の犯罪事実を捜査機関に申告して身柄の処分をゆだねたと認められる関係にあれば、これらの事情を全体として考察し、『いまだ官に発覚せざる前』に自首したものとして刑法四二条一項の自首の成立を肯認することができるというべきである。」
(4)かかる基準に照らし、本件には以下のような事実が認められるとする。
「これを本件についてみると、前記認定のとおり、被告人は、本件犯行直後、自首を決意し、そのまま警察官派出所に赴き同所表出入口に設置されたインターホンを押していること、その時間が犯行の約10分後であり、被告人の妻が110番通報をする約8分も前であって、同所に警察官が駐在しておれば、その時点で自己の犯罪事実を申告して確実に自首が成立したであろうことは明白であること、また、右派出所には、不在派出所用緊急通報装置が設置され、右インターホンにより、石岡警察署通信室との通話が可能であり、右被告人が右のインターホンを押した時点で、右の装置が作動して、右通信室の呼出し音が鳴り、同署警察官が応答したものの、被告人がそのことに気付かなかったため、被告人はやむなく同じ町内の文化センター前の電話ボックスまで移動し、そこから110番通報して自己の氏名と犯罪行為を申告したうえ、そのまま同所にとどまり、さらに駆け付けた警察官の質問に対し自己の氏名、犯罪行為を話して任意同行に素直に応じ、任意同行先の前記警察署において緊急逮捕されるに至ったものであること等の事情が認められる」
(5)そこで、判決はこれらの事実から、以下のような結論を導き得るとした。
「これらを総合評価すれば、被告人の右の行為は全体としてみて、『いまだ官に発覚せざる前』に自首したものと評価することができるというべきである。」
(抜粋の文責:山口貴士)
以上